大阪公立大学ボランティア・市民活動センターV-station 創ラボ(つくらぼ)と連携した取組
更新日:2025年3月5日
大阪公立大学ボランティア・市民活動センターV-stationと中区役所企画総務課、堺市環境局環境事業部資源循環推進課が連携して、エコショップ制度について中区に所在する店舗への登録依頼やイベントにおける周知・啓発を行いました。
創ラボとは
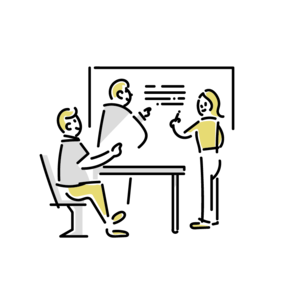
大阪公立大学ボランティア・市民活動センターV-stationの有志のメンバーが集まって、自分たちで興味関心のあるテーマについて話し合い、机上での企画だけでなく、実際の活動を自分たちが行うことまでを含め、一から新たなボランティア活動を創造するプロジェクトです。
第1期(2021年2月スタート)では、フードロスの現状やコロナ禍での生活困窮に対して大学生として何ができるかに着目し、大学生が主体となって家庭で余っている食品や日用品等を必要としている人につなげるというフードドライブ活動を行い、その後も「まんぷくプロジェクト」という名前で、フードドライブ活動の実施を行ったのことです。
大阪公立大学中百舌鳥キャンパスが位置する堺市中区の区役所と協働して地域課題の実情や課題を踏まえた取組を行いたいという申し出があったため、中区役所も一緒に何ができるかを検討しました。
活動経過(概要)
| 回 | 日 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和3年8月26日 | 中区地域計画と同計画に基づく区の取組の紹介 |
中区役所企画総務課/創ラボ |
| 第2回 | 令和3年9月24日 | 取組む分野別要素(”環境”)の決定 | 中区役所企画総務課/創ラボ |
| 第3回 | 令和3年11月1日 | 中区まちあるきオリエンテーション | 創ラボ |
| 第4回 | 令和3年12月8日 | 活動内容の方向性の決定 |
中区役所企画総務課/創ラボ |
| 第5回 | 令和3年12月20日 | 資源循環推進課による堺市の省資源に関する取組の紹介 |
中区役所企画総務課/創ラボ/資源循環推進課 |
| 第6回 | 令和3年12月27日 | 活動内容の決定 | 中区役所企画総務課/創ラボ |
| 第7回 | 令和4年1月12日 | エコショップ登録勧奨の流れについてレクチャー | 中区役所企画総務課/創ラボ/資源循環推進課 |
| 第8回 | 令和4年2月21日 | 登録勧奨店舗候補の決定 | 中区役所企画総務課/創ラボ/資源循環推進課 |
| 第9回 | 令和4年3月24日 | 登録勧奨時アンケートの作成・指導 | 中区役所企画総務課/創ラボ/資源循環推進課 |
| 第10回 | 令和4年3月29日 | 登録勧奨 | 中区役所企画総務課/創ラボ/資源循環推進課 |
| 第11回 | 令和4年4月15日 | 登録勧奨に係る報告 | 中区役所企画総務課/創ラボ/資源循環推進課 |
| 第12回 | 令和4年6月24日 | 登録勧奨2 | 創ラボ/資源循環推進課 |
| 第13回 | 令和4年8月20日・21日 | イベント(雑貨村inソフィア・堺)における周知活動 | 創ラボ |
| 第14回 | 令和4年11月30日 | 活動の振り返り | 中区役所企画総務課/創ラボ/資源循環推進課 |
活動内容
令和3年8月26日 中区地域計画と同計画に基づく区の取組の紹介
まず、中区役所の行政計画として令和3年3月に策定した中区地域計画と、同計画に基づく区の取組について、企画総務課より創ラボのみなさんに説明し、区の現状を把握してもらいました。
中区のめざす将来像「~みんなが安心を感じ、魅力をつなぎ、活力を生む~成長の歩みを止めない中区」を構成する3つの基本要素、7つの分野別要素の中から、参加した学生メンバー各々が興味のある分野について調べ、どのような取組ができるかを考えたうえで、グループとして取り組むテーマを決定することとなりました。
令和3年9月24日 取組む分野別要素(”環境”)の決定
創ラボのメンバーがそれぞれ考えてきた興味のある分野や、こんなことができそうだという取組のイメージを発表してもらいました。
子育てや健康に関する施策などの提案もありましたが、それらの分野については子育て支援課や中保健センターがすでに取り組んでいる内容も多く、まだ区の取り組みが手薄な部分として「分野別要素:環境」の「省エネルギー化・省資源化の推進による循環型地域社会の実現」について取り組んでいくことを決定しました。次回の集まりに向けてメンバーには、堺市が現在取り組んでいる事業を調査し、また他市などで実施している事業などで参考になるものがないかを調べてきてもらうこととしました。
令和3年11月1日 中区まちあるきオリエンテーション
創ラボのメンバーから、大学には通っているものの、大学以外で中区内を移動したり、どこかを訪れたりといったことがほとんどないため、実際に中区内をめぐり、中区についてもっと知りたいとの申し出がありました。
メンバーは、大阪公立大学中百舌鳥キャンパスを出発し、国指定史跡である史跡土塔や、鈴の宮神社、蜂田神社などの歴史的資源を訪れ、市の伝統産業である注染の工場を見学し、染め体験を行いました。
また、水賀池公園や原池公園など、区民の憩いの場、運動の場となっている公園施設も訪れ、自分が通う大学のあるまちやそこで暮らす人たちを見る貴重な機会が得られたと喜んでいました。
毛穴の工場で染め体験
原池公園
令和3年12月8日 活動内容の方向性の決定
「分野別要素:環境」の中で省エネルギー化に関する問題などについては、自分たちができることはあまり多くないのではないか、それよりも「省資源に関する区民の意識啓発」のような、身近な生活環境についての問題であれば力になれるのではないかとの提案が学生からあったため、「一般廃棄物の減量化や資源化並びに適正な処理に関する情報発信」を所管業務とする環境局の資源循環推進課とも協働して、中区内のごみ等の省資源化に関する取組を企画していくという方向性を決定しました。
令和3年12月20日 資源循環推進課による堺市の省資源に関する取組の紹介
環境に関する堺市の取組をより詳しく創ラボのメンバーに知ってもらい、企画検討の助けとするため、資源循環推進課の職員からごみ等の省資源化に関する出前授業を行いました。
出前授業を受講したメンバーからは、堺市のごみ等に関する現状や取組について具体的に教えていただいたことで、これからの活動において具体的にどのような問題に焦点を当てるべきなのかが明確になったとの感想が得られました。
令和3年12月27日 活動内容の決定
堺市が現在実施している省資源に関する取組の中で、エコショップ制度の周知・啓発をすることで店舗の方や、そのお店を利用する方の省資源化に関する意識を高められるのではないか、登録店舗を増やすために自分たちが何か協力できるのではないか、と学生から提案があり、エコショップの登録店舗増加を目標として活動することを決定しました。
大学生が比較的まとまった時間を確保できる大学の春休み期間中(2~3月)に勧奨に訪れる店舗のリストアップや勧奨時に協力をお願いするアンケート作成の準備をし、実際に中区内の店舗に登録の勧奨に行くことを決めました。
令和4年1月12日 エコショップ登録勧奨の流れについてレクチャー
創ラボのメンバーがエコショップの登録勧奨をするにあたり、エコショップの概要について、チラシやHPを見せながら、店舗の方にわかりやすく簡潔に伝えられるよう、資源循環推進課の職員からレクチャーを受けました。
メンバーからは、実際に店舗の方にどのように話を進めるのかを順序立てて教えていただき、訪問する際のイメージが湧きましたとの感想が得られました。
令和4年2月21日 登録勧奨店舗候補の決定
創ラボのメンバーたちがインターネット等で調べた中区に所在する店舗から、環境にやさしい取組を行っていそうな店舗をリストアップし、実際に勧奨に訪れる店舗を決定しました。また、登録時に店舗の方にアンケート調査を行い、今後の登録店舗の増加等の取組の参考としたいとの意見も出たため、次回までに創ラボのメンバーがアンケート案を作成し、中区役所及び資源循環推進課が確認し、手直しをすることとしました。
令和4年3月24日 登録勧奨時アンケートの作成・指導
メンバーが作ったアンケート案の内容について確認し、修正などを行って一緒にアンケートを完成させました。
アンケートには、エコショップに登録された店舗について、どのような広報がなされれば嬉しいか、環境にやさしい取組をすることに対する意欲、今既にやっている以外にどんなエコな取組ができるか、他にどんな企画や制度があれば協力したいと思うかなどについての質問項目を設けました。
メンバーからは、紙で取るアンケートとは別にQRコードを読み取って答えられるようにもしておけば、そのときは忙しくても後で時間があるときに答えてくれるのではないか、など店舗側の負担を考慮した意見も出されていました。
令和4年3月29日 登録勧奨

創ラボのメンバーたちが、資源循環推進課の職員と一緒に実際に中区内の店舗を訪れ、自分たちの活動目的や内容、エコショップ制度について説明を行い、精力的に登録勧奨に努めました。
初めての店舗訪問だったため、思うように話がまとまらないこともありましたが、お店の方にも学生の活動に興味を持っていただけることが多く、中にはお店の環境にやさしい取組について説明してくださるところもありました。
想像していた以上にエコな取組をすることに興味を持っているお店が多く、これからの活動においてとても参考になりました。
令和4年4月15日 登録勧奨に係る結果報告
登録勧奨を行った店舗のうち、「武市畳店」、「DIY Shop MANAboo」の2つの店舗がエコショップに登録してくださいました。
創ラボのメンバーは、実際に登録勧奨に訪れた店舗にエコショップに登録していただけたという目に見える成果を得られたことで、自分たちが店舗訪問に行くことに意味があるのだと実感でき、これからの活動のモチベーションに繋がりましたと喜んでいました。
令和4年6月24日 登録勧奨2
2度目の登録勧奨は様々な事業を地域で展開しておられるセルビスグループにお話しをさせていただきました。
店舗への登録勧奨ではなく、本社へ伺って登録勧奨を行うということで、学生は少し緊張していた印象でした。
しかし、エコショップの制度などについては学生が滞りなく説明し、セルビスの担当者様も学生の様子に関心している様子でした。
セルビスグループの担当者様は、大学生の活動にとても興味を示してくださり、会社としてどのようなエコな取組を行っているのか、エコな取組を行うにはどのような問題があるのか等を会社側の視点から教えてくださりとても参考になりました。
令和4年8月20・21日 雑貨村inソフィア・堺における周知活動
雑貨村inソフィア・堺においてブースを出展し、パネルや冊子を用いて、イベントに訪れた市民の方や、出展されている店舗の方にエコショップ制度についての周知・啓発を行いました。
創ラボのメンバーからは、これまでの活動の成果を発表する場であるブースを出展してみて、準備不足だった面もあったものの、イベントに訪れた市民の方に対して直接啓発ができ、少しでも区民の環境意識の改善に貢献できてよかったという意見が得られました。



令和4年11月30日 活動の振り返り
これまでの活動を踏まえ、中区役所、資源循環推進課、創ラボのメンバーで振り返りを行いました。
1年以上に渡る活動を終え、達成感を得たことや、反省すべき点、今後の創ラボのあり方等について意見を交換しました。
創ラボメンバーの感想
陳代 修平さん(工学域 機械系学類 3年)

中区役所の方々には別の活動でお世話になった経験もあり今回の活動にも参加しました。
今回の活動では、区として課題に感じているとお聞きした分野の中から「環境」分野に取り組むことになったので、活動がそのまま区のためになっていると感じやすかったです。
区役所や市役所の方のサポートのおかげでみんなが仲良く進められ、中区のことや環境のことなどの学びもたくさんあったので、今回の経験を今後の活動にも活かしていければ良いなと思います。
小倉 弓果さん(生命環境科学域 緑地環境科学類 3年)

今回の取り組みでは、既にやることが決まっている活動に参加するというのではなく、中区の良くしたい部分を見つけるところから始めて、実際に行う方法も自分たちで考えていく、という過程を踏んでいけたことが私にとっては良い経験になりました。
活動の成果としてはもっと頑張れたなと悔しく思う部分もありますが、アクションを起こすことで、少しずつでも市民の方のエコ意識に働きかけることができたのであればうれしいです。
貝谷 理穂子さん(工学域 電気電子系学類 3年)

私は何か自分の住んでいる街に貢献できるようなことをしたいと思いこの活動を始めました。実際にお店を訪問して話をし、制度を理解してもらうのは非常に難しいことだと感じました。それでも登録店舗を2店舗増やし、さらにイベントに参加して市民の方々とも交流することで、少しは街に貢献できたかなと思います。
この活動はコロナでうまくいかないことも多かったのですが、役所の方々の全面サポートがあり、1年間続けることができました。非常に良い経験をさせてもらいました。
檀野 ことねさん(現代システム科学域 環境システム学類 2年)

大学のある堺市中区をより良くしたいという漠然とした目的から街の様々なことに目を向け、自分たちで何をするのか一から考え実行することはとても難しいことでしたが、その分やりがいもありとても良い経験になりました。
コロナ禍で思うように活動ができないこともありましたが、堺市や中区のこと、環境問題、人とのコミュニケーションなどこれからの活動にも生かせる様々なことを活動の中で学ぶことができ、成長することができました。
高田 彩加さん(生命環境科学域 応用生命科学類 4年)

私は、通っている大学がある地域のことをもっと深く知りたいと思い、この活動に参加しました。中区の地域計画から課題点を見つけ、私たちが出来ることを考え、実際に活動していくという過程は、貴重な体験となりました。
一方で、市民の方々に、行政の取り組みを伝えることや協力を得ることの難しさを感じました。この活動を通して、環境に対する意識や学びをより深いものにすることができ、中区だけでなく、自分が住んでいる地域のことも見直すきっかけとなり、いい経験になりました。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

