無形文化遺産関連事業 平成29年度(2017年度)事業
更新日:2024年7月1日
無形文化遺産理解セミナー、展示、ワークショップなどを開催します。
開催概要・参加者募集などの情報は決まりしだい随時掲載します。興味のある方は是非チェックしてください。
NEW第20回無形文化遺産理解セミナー ベトナムの舞台芸術-フエ宮廷雅楽とカーチューを中心に 定員に達したため、募集が終了しました。
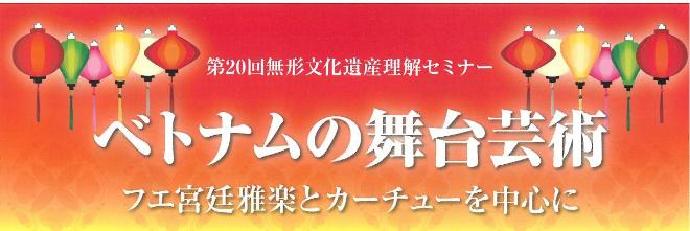
ベトナムの旧正月「テト(2月16日)」の前に、甘いベトナムコーヒーを飲みながら、堺市と歴史的に深い関係のあるベトナムの無形文化遺産のお話を聞きませんか。
ユネスコ無形文化遺産代表一覧表及び緊急保護一覧表に登録されているものから、フエ宮廷雅楽(ニャー・ニャック)とカーチュー(歌籌)という二つの芸能を取り上げ、その歴史と現状、そして魅力を紹介します。また、ハノイ観光でお馴染みの水上人形劇など、将来ユネスコ無形文化遺産に登録される可能性があるものを含め、他のいくつかの民間芸能にも触れ、ベトナムの舞台芸術全体を概観します。
講演に先立ち、ベトナム文化の雰囲気を体感できるように、ベトナムコーヒーの淹れ方の実演を行い、希望の方には有料で飲んでいただくこともできます。
日時
平成30年2月3日(土曜) 午後1時~3時30分
・午後1時~1時50分 ベトナムコーヒーの淹れ方実演
・午後2時~3時30分 講演
会場
堺市博物館ホール
主催
堺市
協賛
エースコック株式会社
プログラム
- 午後1時00分から1時50分 ベトナムコーヒーの淹れ方と実演
講師:トミザワ ユキ ベトナム料理研究所 主宰
ベトナムコーヒーの淹れ方を実演して、その淹れ方と味の特徴などを紹介します。先生とベトナムのカフェや食文化の話をしながら、リラックスにコーヒータイムをお過ごしください。
※コーヒーをお飲みになる方は参加申込の時にお伝えください。1杯300円
- 午後2時から3時30分 講演:ベトナムの舞台芸術-フエ宮廷雅楽とカーチューを中心に
講師:伊澤 亮介 滋賀短期大学 特任助教
ベトナムはユネスコ無形文化遺産代表一覧表及び緊急保護一覧表に11件の無形文化遺産が登録されています。その中から、フエ宮廷雅楽(ニャー・ニャック)とカーチュー(歌籌)という二つの芸能を取り上げ、その歴史と現状、そして魅力を紹介します。
フエ宮廷雅楽は、15世紀にベトナムの王朝が中国明朝からその制度を受け入れ、徐々にベトナム独自のものを加えながら形成された、宮廷の儀式のために形式化された音楽、舞踏です。また、カーチューも初め宮廷や貴族、知識人の間で楽しまれ徐々に民間に広まった、女性が楽器の伴奏に合わせて詩歌を歌い上げる芸能です。
さらに、ハノイ観光でお馴染みの水上人形劇など、将来ユネスコ無形文化遺産に登録される可能性があるものを含め、他のいくつかの民間芸能にも触れ、ベトナムの舞台芸術全体を概観します。
定員
100人 参加無料(コーヒー有料)、要申込、先着順
申込方法
ファックス、電話、電子メール又は電子申請システムでお申込みください。ファックス、電子メール・電子申請システムの場合、参加希望者全員の必要事項(住所、氏名(ふりがな)、電話・ファックス番号)、コーヒー希望の有無及び杯数を明記してください。
1月9日(火曜)午前9時30分から、受付開始。
お申込・お問い合わせ先
堺市博物館 無形セミナー係
- 〒590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁(大仙公園内)
- 電話:072-245-6201(直通) ファックス:072-245-6263
- 電子メール:こちら(お問合せメール)
- 電子申請システム:受付終了
プレゼント
参加者にエースコック株式会社ご提供の「Pho・ccori気分鶏だしフォー」(袋)をプレゼントします(一人一点)。


第20回無形文化遺産理科セミナー「ベトナムの舞台芸術-フエ宮廷雅楽とカーチューを中心に」チラシ(PDF:1,786KB)
第19回無形文化遺産理解セミナー 人形浄瑠璃文楽の歴史 <終了>
日時
10月28日(土曜)午後2時から3時30分まで
会場
堺市博物館ホール
主催
堺市
講師
久堀 裕朗 大阪市立大学大学院文学研究科 教授
内容

今回のセミナーでは、人形浄瑠璃文楽が現在のような形になるまでの変遷や文楽が大阪を代表する伝統芸能と言われる理由などについて、映像や音声を交えながら説明していただきました。講演内容は次のとおりです。
◎浄瑠璃は語り物の一つで、15世紀後半に人形を伴っていない「浄瑠璃御前物語」が京都に伝わった。
◎人形を操る芸は古代からあったが、江戸時代に入った頃、西宮戎舁(えびすかき)の芸が浄瑠璃と合体し、人形浄瑠璃が誕生した。中世の終わり、近世(江戸時代)の始めに人形浄瑠璃が京都で発祥し、京都、大坂、江戸などの都市で興行が始まった。
◎1600年代、義太夫節以前の古い浄瑠璃各派の総称を古浄瑠璃といい、人形は一人遣いであった。現在、古浄瑠璃の実態はよく分かっていないが、地方で伝承されているケースが多く、その一つが佐渡島の文弥人形である。
◎江戸時代、人形浄瑠璃は歌舞伎と人気を二分していた。
17世紀後半には竹本義太夫が現れ、竹本座を創設して人気を集めるようになり、以後、義太夫節人形浄瑠璃のみが伝承された。
◎1700年代初め、人形浄瑠璃は一人遣いの時代であった。舞台には手すりがあって、太夫の床はなく、太夫は手すりの後ろの見えないところで語っていたが、道行など特別な場面のみ、手すりの前の付舞台に出て語った。しかし、18世紀末には現行の舞台様式が定着した。
◎「浄瑠璃譜」によると、人形の三人遣いは「芦屋道満大内鑑」からであると考えられるが、この時からすべての人形が一斉に三人遣いになった訳ではなく、徐々に現在の三人遣いの形態が整っていったと考えられ、18世紀半ば頃には現在のような三人遣いが定着した。
◎元禄時代、道頓堀には義太夫節人形浄瑠璃を上演していた竹本座に加え、竹本座のライバルとなる豊竹座も創設された。道頓堀の西側と東側にあった竹本・豊竹両座の活躍は、芝居町としての道頓堀に繁栄をもたらすことになった。
◎寛政(1789-1801)頃、正井文楽が大坂で浄瑠璃の稽古場を始め、その後、二代目文楽軒が博労町稲荷境内(難波神社境内)へ進出した。江戸時代、文楽が経営する芝居小屋(劇場)は通称「文楽の芝居」と呼ばれていたが、明治になって文楽座を名乗るようになった。他の劇場が絶えていく中、文楽座が都市部で唯一の人形浄瑠璃劇場となり、「文楽」がこの芸能自体を表す語となっていった。
◎単に「文楽の歴史」というと、狭い意味では江戸時代後期以降のことになるので、そうではなく広い意味での「文楽(人形浄瑠璃)」を表したい場合には、「人形浄瑠璃文楽」という語を用いたりする。
第19回無形文化遺産理解セミナー「人形浄瑠璃文楽の歴史」チラシ(PDF:1,608KB)
第18回無形文化遺産理解セミナー・ワークショップ 能楽へのお誘い-Do You 能? <終了>
能楽は室町時代に大成された日本を代表する古典芸能で、重要無形文化財に指定されています。2008年に、ユネスコ「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に登録されました。
今回は、文化継承の担い手である小中学生にもっと日本の伝統文化に触れていただくために、夏休み期間中に、「能楽」が体験できる無形文化遺産理解セミナー・ワークショップを開催します。
能楽の仕舞(しまい)を鑑賞し、能楽の歴史などのお話を聞いたあと、能の謡(うたい)をうたってみたり、能面や能装束の美しさにふれたりしていただきます。子どもも、大人も、だれでも気軽に楽しく参加できる内容になっています。
ぜひこの機会に、能の世界を体験し、お楽しみください。
日時
8月19日(土曜)午後2時~4時

会場
堺市博物館ホール
主催
堺市
講師
山本章弘 公益財団法人山本能楽堂 代表理事/観世流能楽師・重要無形文化財総合指定保持者
定員
100人 参加無料 要申込 先着順
申込方法
電子メール・電子申請システムまたはファックス、電話で、参加者全員の氏名(ふりがな)、住所、電話・ファックス番号を明記の上、下記お申込・お問合せ先までお申し込み下さい。7月20日(木曜)午前9時30分から受付開始。
お申込・お問い合わせ先
堺市博物館 無形文化遺産係
- 〒590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁(大仙公園内)
- 電話:072-245-6201(直通) ファックス:072-245-6263
- 電子メール:こちら(お問合せメール)
- 電子申請システム:受付終了
第18回無形文化遺産理解セミナー・ワークショップチラシ(PDF:1,045KB)
NEW 無形文化遺産理解事業2017 生と死、先祖と子孫を結ぶ儀礼-アジア諸国の葬儀と祖先祭祀
葬儀と祖先祭祀は諸文化の死生観、家族形成や世代継承などに関わる考え・認識の表れであり、ユネスコ無形文化遺産の重要な要素であります。ユネスコ「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に記載されているものとして、韓国の「宗廟祭祀と宗廟祭祀楽」とメキシコの「死者に捧げる原住民の祭礼」が挙げられます。
今回の無形文化遺産理解事業では、アジア諸国の葬儀と祖先祭祀をテーマに、コーナー展示、無形文化遺産理解セミナー及びワークショップを開催します。
また、7月から堺市博物館で実施する、世界遺産登録をめざす百舌鳥・古市古墳群に関連する企画展「シークレット・オブ・KOFUN-古墳のカギを見つけてみよう-」にあわせ、有形と無形の文化遺産の関係性についても理解を深めていただきます。
主催:堺市
特別協力:国立民族学博物館
コーナー展示 祖先祭祀-アジア諸国の祀り-
 写真撮影:潘宏立
写真撮影:潘宏立
期間
平成29年8月1日(火曜)~9月10日(日曜)
会場
博物館展示場内
概要
企画展「シークレット・オブ・KOFUN-古墳のカギをみつけてみよう-」のテーマである古墳にも深くかかわる祖先への祀りや葬送の祀りについて、現在アジア諸国で行われているこれらの祀りの一部を紹介します。
第17回無形文化遺産理解セミナー 旧暦7月に祖先を迎え、送る人びと-中国雲南省の事例から東アジアの祖先祭祀を考える <終了>
日時
平成29年8月5日(土曜) 午後2時から3時30分まで
会場
堺市博物館ホール
定員
100人(先着順。申込方法は下記参照)、参加無料
講師
横山 廣子 国立民族学博物館 教授
概要
琵琶湖のような美しい湖のある中国雲南省大理盆地には、日本のお盆によく似た行事をおこなう人びとがいます。毎年、旧暦7月になると、家の前で火を焚いて祖先を迎え、祭祀の後に祖先を再びあの世へと送ります。大理は唐代に南詔国の都がおかれ、そこに今も住む人びとは、中国の少数民族、ぺー族です。
大理のぺー族と日本とは遠く離れていますが、不思議な縁で結ばれています。南詔が派遣した使者は、唐朝の宮廷で日本の遣唐使、圓仁と同席しています。また元代末期、日本人僧が大理に滞在し、そこで生涯を終えました。彼らのために建てられた塔は「日本四僧塔」として知られ、今も湖を見下ろす斜面に残っています。
中国の漢文化を積極的に受容する一方、漢族以上に仏教が日々の生活に浸透しているぺー族の祖先祭祀は、漢族的であると同時に、彼ら独自の展開が見られます。ぺー族の祖先祭祀を踏まえて、中国、韓国、日本の祖先祭祀のあり方の違いについても考えます。映像を多くお見せしながら、御話しします。
申込方法
電子メール・電子申請システムまたはファックス、電話で、参加者全員の氏名(ふりがな)、住所、電話・ファックス番号を明記の上、下記お申込・お問合せ先までお申し込み下さい。7月3日(月曜)午前9時30分から受付開始。
お申込・お問い合わせ先
堺市博物館 無形文化遺産係
- 〒590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁(大仙公園内)
- 電話:072-245-6201(直通) ファックス:072-245-6263
- 電子メール:こちら(お問合せメール)
- 電子申請システム:受付終了
ワークショップ 記録映像で見るお葬式と祖先祭祀の儀礼 <終了>
日時
平成29年8月5日(土曜) 午後12時30分~午後1時30分
会場
堺市博物館 展示場、博物館ホール
講師
橘 泉(当館学芸員)
定員
50人 参加無料(観覧料必要)、申込不要、当日先着順
概要
展示品解説のあと、アジア諸国の葬式や祖先祭祀の儀礼を記録した民族誌映画等を鑑賞し、映像を通して葬儀や祖先祭祀の儀礼のプロセスを観察します。
無形文化遺産理解事業2017チラシ(PDF:1,005KB)
東京シンポジウム2017-文化遺産を考える-<終了>
内容
本シンポジウムは、歴史文化を活かした堺市独自の取組みを通じて、首都圏での本市の知名度向上及び世界文化遺産登録への機運醸成を図ることを目的に、2015年から実施している東京シンポジウムの第3弾として開催しました。
佐々木 丞平 京都国立博物館長による基調講演では、文化国家の基本条件は国民のモラルであるということ、また、我が国なり、都市に対してナショナル・アイデンティティーを明確に自覚しておくことである、そして、国の諸施策の中で文化というものがいいバランスで位置づけられていることが重要であるというお話しがありました。
吉田 憲司 国立民族学博物館長による基調講演では、博物館は単に過去の物の貯蔵庫や一方的な表象、展示の装置としてではなく、そこに立場を異にするさまざまな人々が集って相互の交流と啓発を重ねる中で、過去の文化を創造的に継承し、新たな文化と社会をつくり上げるフォーラムとしてのミュージアムに大きく動き出しているというお話しがありました。
続いて行われた事例発表では、中島 誠一 前長浜市曳山博物館長からは、ユネスコの無形文化遺産に登録された長浜曳山まつりの継承と同館の役割などについて、岩本 渉 アジア太平洋無形文化遺産研究センター所長からは、同センターの活動とユネスコが推進する無形文化遺産の保護・継承の意義などについて、籔内 佐斗司 東京藝術大学教授からは、同大学で人材育成している保存修復技術が文化財保護に果たす役割や国際貢献などについて、発表していただきました。
最後に、東京楽所による雅楽公演が行われ、バラエティに富んだ演目が披露されました。
概要
日時
2017年6月3日(土曜) 午後1時から午後4時30分 (開場正午12時15分)
会場
東京国立博物館 平成館大講堂(東京都台東区上野公園13-9)
佐々木 丞平 京都国立博物館長
主催
堺市、国立文化財機構
後援
文化庁、国立民族学博物館、
百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議
プログラム
=基調講演=
吉田 憲司 国立民族学博物館長
- 演 題:「文化・文化財・文化都市を考える」
講 師:佐々木 丞平 京都国立博物館長
- 演 題:「無形文化遺産とミュージアム-UNESCOにおける無形文化遺産保護条約成立から15年の時を経て」
講 師:吉田 憲司 国立民族学博物館長
=事例発表= 「無形文化遺産の取組み、その最前線で」
(発表者)(50音順)
・岩本 渉 アジア太平洋無形文化遺産研究センター(IRCI)所長
・中島 誠一 前長浜市曳山博物館長
・籔内 佐斗司 東京藝術大学教授・堺名誉大使
(進行)
・須藤 健一 堺市博物館長
=雅楽ミニ公演= ~百舌鳥古墳群の映像とともに~
東京楽所
解説:代表 多 忠輝 氏
演目:壱越調音取
朗詠 嘉辰(和漢朗詠集 祝より) 他
=ロビー展示=
- アジア太平洋無形文化遺産研究センター(IRCI)の紹介
※堺市博物館内で開設後、堺市と連携した事業なども実施しています。
- 百舌鳥古墳群の紹介
東京シンポジウム2017-文化遺産を考える-チラシ(PDF:1,141KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
文化観光局 歴史遺産活用部 博物館 学芸課
電話番号:072-245-6201
ファクス:072-245-6263
〒590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁 大仙公園内 堺市博物館
このページの作成担当にメールを送る