建築協定を結ぶには
更新日:2012年12月19日
合意形成について
協定の発意
多くの人々が“自分たちの住環境が悪化する”と危機感(現状の問題・課題)を抱いたときに、建築協定を結ぼうという気運が高まってきます。しかし、危機感を抱いても思いつかなければ何も始まりません。建築協定を結ぼうという思いつきは、個人や数人の会話から始まります。その機会を大切にしてください。
協定締結のための組織づくり
協定の締結は、住民の主体的・自発的な行動ですので、特に住民による組織づくりは重要です。協定を結ぼうという機運が高まれば、まず「準備委員会」を結成し、合意形成のため活動を開始します。
合意形成の効果的方法
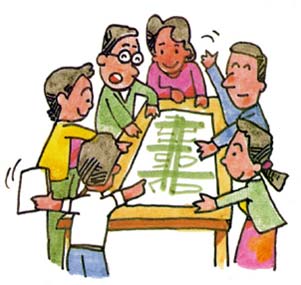
住みよいまちづくりのための話し合いを重ねていくには、まず、まちづくりや協定についてアンケート調査をおこない、地域住民の意識を確認することから始まります。そして、頻繁に話し合いや説明会や勉強会を重ね、また、欠席者の意見を尊重するために戸別訪問なども実施します。それらの積み重ねが協定を締結するための組織づくりにもなります。
認可申請について
認可申請に向けて
協定が成立するためには、「合意形成」が最も大切です。準備委員会のもと、協定区域を想定し、登記簿や公図などから土地の所有者や権利者を調べます。そして、みんなで説明会や勉強会、自治会の総会などの機会に協定をするかどうか話し合います。全員が建築協定をすることに合意をすれば、協定の認可手続きの準備を進めます。
認可申請の準備にあたっては、まず、協定を締結しようとする人びとの中から民主的な方法で複数の委員を選出し、さらにその中から代表者を選びます。選ばれた代表者及び委員により、具体的に協定認可申請書類を作成します。
合意書の作成にあたって
協定の締結には、土地の所有者等の全員の合意が前提となります。
そのためには、不在地主などの実態や地権者の実情をあらかじめ十分に調べ、書面や訪問で理解を求めるとともに、地域内の各種の専門家に協力を依頼し、準備委員会に参加してもらっておくと、種々の問題に対しアドバイスを受けられ円滑に事務を行うことができます。
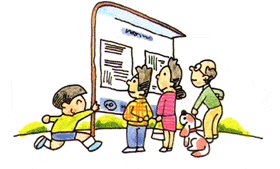
〔必要提出書類〕
【1】建築協定認可申請書
【2】建築協定書
【3】建築協定区域図・位置図など
【4】合意書(代表者の選任事項を含む。)
【5】その他
合意のすすめ方から協定認可までの流れ
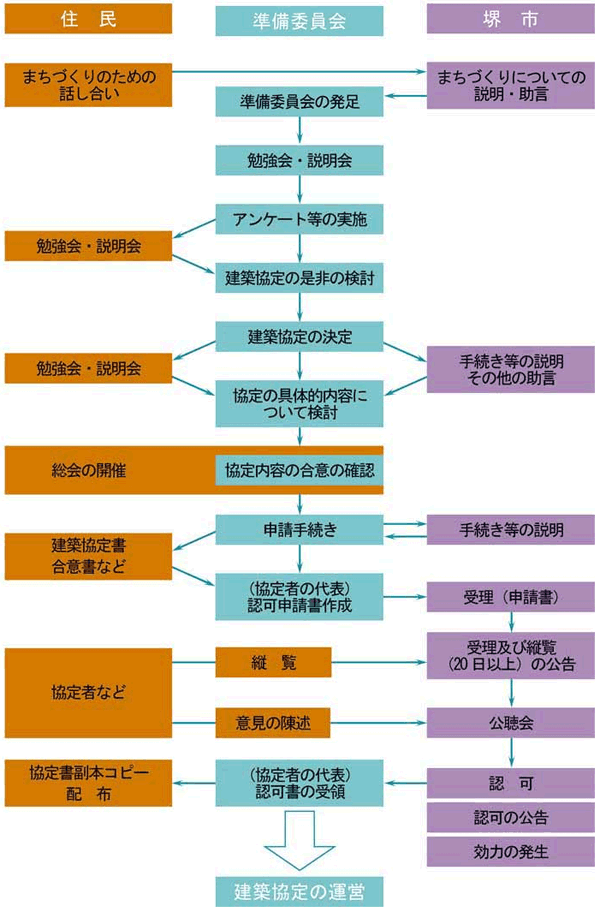
このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築安全課
電話番号:072-228-7936
ファクス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階
このページの作成担当にメールを送る