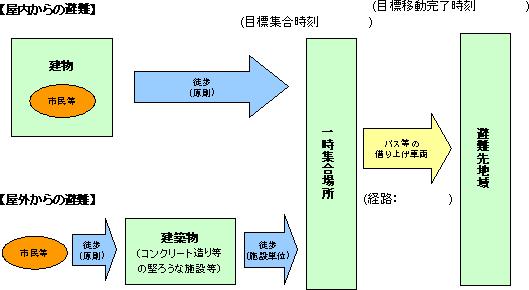2) パターン【1】(応急避難)
更新日:2012年12月19日
1.事態想定
災害が発生し、災害発生現場において、市民等(一時滞在者を含む)が当面の身の安全を確保する必要が生じている。
2.発生現場付近でとるべき行動
[1]屋外にいる場合 最寄りの堅牢な建物や地下施設への避難
- その場から直ちに離れ、外気から密閉性の高い屋内の部屋、あるいは風上の高台等の汚染の恐れのない安全な地域に避難する。
- ビニール袋、ハンカチ等で口・鼻を覆い、襟を立て、腕まくりを解くなどにより暴露皮膚を少なくする。
- 公共交通機関で移動中の場合には運行者の指示に従う。
- 自家用車で移動中の場合には周辺状況に留意しつつ停止し、広報車、公共放送等により情報を入手し車内に待機、あるいはビニール袋、ハンカチ等で口・鼻を覆い、襟を立て、腕まくりを解くなどにより暴露皮膚を少なくしてその場から直ちに離れ外気から密閉性の高い屋内の部屋、あるいは風上の高台等の汚染の恐れのない安全な地域に避難する。
避難の際には車を道路の左側に寄せエンジンを停止し、鍵はつけたままにする。
[2]屋内にいる場合
- 直ちに出入り口、窓等の開口部を閉鎖する。
- エアコンや換気扇等の空調機器を停止、さらに必要に応じてビニールテープ等で目張りをして外気を遮断する。
- ドア、壁、窓ガラスから極力離れ、部屋の中心部に留まる。
- できるだけ高い階へ移動する。
[3]長期化に向けて
屋内避難の長期化(1日以上)、二次避難への移行を想定し、最低限の現金や通帳等の貴重品、最低必要物資を収納した非常持出品を準備する。
3.特殊な状況下での留意事項
[1]化学剤・生物剤・放射性物質散布の場合
- 汚染された服、時計・装飾品、眼鏡・コンタクトレンズ等は速やかに処分する必要があるが、汚染された衣服を脱ぐ際には、露出している皮膚に汚染部分が触れることのないように留意する。頭から被るセーターのような服の場合には、はさみを使用して切り裂いて身体から離す。
- 二次汚染防止の観点から、汚染されたものはビニール袋(極力二重にする)に密閉し管理する。また、処分後は水と石鹸で手、顔、体を良く洗う。
- 汚染物質に接触したと疑われる場合には、頭からつま先まで大量の水で洗い流す。石鹸(アルカリ性)が用意可能な場合には、水で洗い流し、石鹸で洗い、最後に水で洗い流す。洗浄の目安は3から5分程度を考える。
- 同時に、汚染の事実を周囲の人間に知らせるとともに、避難誘導単位リーダー、警察・消防に通報する。
- 安全が確認されるまでは、汚染された可能性のある水・食料は摂取しない。
[2]爆発等の現場に遭遇した場合
- 先ず爆発に遭遇した場合には、とっさに姿勢を低くして、身の安全を確保する。
- 周囲で落下物等がある場合には、遮蔽物を利用して極力身体の露出を少なくする。
- その後、落ち着いて爆発地点から極力速やかに離れるようにする。
放射性物質拡散の危惧がある場合
- ビニール袋、ハンカチ等で口・鼻を覆い、襟を立て、腕まくりを解くなどにより暴露皮膚を少なくしてその場から直ちに離れ外気から密閉性の高い屋内の部屋、あるいは風上の高台等の汚染の恐れのない安全な地域に避難する。
- 爆発規模が小さかったからといってむやみに爆発現場には近づかないようにする。
- 数kmの範囲で放射線が拡散する恐れがあるため、安全が確認されるまでは、体内被曝を避けるために汚染された可能性のある水・食料は摂取しない。
- 関係機関により安全が確認されるまでは、原則的に屋内に留まる。
- 万一の被爆の可能性を考慮し、避難解除後に医師の診察を受ける。
[3]予想外の事態に遭遇した場合
- 大声で異常事態の発生を周囲に伝える。
- 事態発生現場から冷静に遠ざかる。(原則風上方向)
- 最寄りの警察、消防機関に対して事態の発生を連絡する。
- 施設等にいる場合には、施設管理者、職員等に直ちに連絡する。
- 共助の観点から、避難に支障を来たしている者がいる場合には、自分自身の安全を確保の上で支援する。
4.災害時要援護者への対応(今年度検討中)
[1]障害者・高齢者・妊産婦・幼児
- 堺市対策本部は、市で把握しているデータや、社会福祉協議会、民生委員児童委員、民間福祉事業者、障害者団体を通じて速やかに応急避難(退避)支障の有無、必要な支援内容を確認し、応急避難(退避)を支援する
- 共助の観点から、地域住民に対して自分自身の安全を確保の上での支援を要請する
[2]在留外国人(観光客等の短期滞在者を含む)
- 予め用意(録音)した避難放送を、駅、その他施設、広報車で実施(日本語+その他外国語:英語、中国語、ハングル、ポルトガル語)
- テレビ、ラジオで避難放送の実施を要請(日本語+その他外国語:英語、中国語、ハングル、ポルトガル語)
- 市ホームページに留意事項を掲載
5.要避難地域における屋外残留者への対応
二次被害防止の観点から必要な防護措置を十分に講じた避難支援班(防護服・マスクの着用等)を派遣し、要避難地域内を巡回し屋外残留者の確認、救出に当たる。
6.避難(退避)の指示・避難実施要領の通知等
堺市対策本部は、避難(退避)の指示、それを受けて作成した避難実施要領(別紙の基本様式1参照)を、下記関係機関等へ通知・伝達する。
[1]市の他の執行機関への通知
機関名、連絡先等詳細は<伝達通知先リスト>参照
[2]関係機関への通知
機関名、連絡先等詳細は<伝達通知先リスト>参照
[3]避難の対象となる避難誘導単位への伝達
単位名、対象者、伝達方法詳細は<伝達通知先リスト>参照
[4]関係団体等への伝達
団体名、連絡先等詳細は<伝達通知先リスト>参照
[5]避難実施要領の放送事業者・報道関係者への連絡等
- 広報課を通じて、堺市政記者クラブを中心に行う。
- 指定(地方)公共機関に対しては、府と調整した上で必要な場合に連絡する。
追記 応急避難後の小単位での避難
応急避難後に移動する必要が生じた場合には、下記のとおり避難を実施する。
- 応急避難後の避難所・一時集合場所への避難対応については、市からの指示に従うことを原則とする。
- 各小単位は、市から伝達された避難開始のタイミング、一時集合場所、避難経路に従い避難を実施する。
- 小単位のリーダーは、各避難者の状況を踏まえ無理な避難行動は避ける。
- 市から伝達された避難の実施に当たって不明点がある場合、あるいは困難が予期される場合には、避難着手前に速やかに市に対してその旨を連絡、指示・支援を要請する。