令和6年度 就学前教育・保育施設等対象研修について
更新日:2025年3月26日
幼児教育研修会
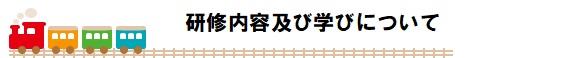
| 講師 | 研修テーマ「主体的な遊びを促す環境と援助」 |
|---|---|
鳴門教育大学 |
主体性の根っこは自己肯定感ということ、こどもの「できるかもしれない、やってみたい」という気持ちを支える環境の大切さを学びました。主体性とは何かを実際の教育保育の様子を見て具体例をききながら、自身の教育保育を振り返ることができました。こどもが主体的にあそべる「種と仕掛け」をちりばめた環境構成をする大切さを改めて実感し、保育者はこどもの「夢」を叶える手助けをする仕事という言葉が印象的でした。 |
| 講師 | 研修テーマ「実践に活かす記録と教育・保育の振り返り、子どもの理解と援助」 |
|---|---|
四天王寺大学 |
こどものエピソードのワークでは教育・保育の振り返りとなり、こどもが何をしたいのか汲み取り対応する大切さや記録を通してのこども理解等、保育観を見つめる時間となりました。こども一人一人の行動、その裏にある思いをよく観察し、記録し、振り返ることが次の教育保育の展開に結び付くことがよくわかりました。グループワークを通し、自分では気づかなかった点を教えてもらい、保育者間での話し合いの大切さを実感しました。 |
| 講師 | 研修テーマ「保護者支援の連携と子育て支援」 |
|---|---|
オフィステラ |
現代の子育て世帯の「核家族化、弧育て」を理解し、保護者の話を聞くときは困り感を把握し、「傾聴」を意識し、心の内を映し出す「心の鏡」となれるように対応すべきことを学びました。 |
| 講師 | 研修テーマ「こどもの人権を守り、育む~こどもまんなかとは~」 |
|---|---|
常磐会短期大学 |
大人の発した一言で大きく傷つくこどもがいることを改めて実感し、言葉の選び方や専門職としての倫理観を振り返る時間となりました。 |
| 講師 | 研修テーマ「園運営と危機管理の対応(BCPの策定を含む)」 |
|---|---|
一般社団法人 |
こどもの命を守るために、災害時を実際に想定し、「どう動けば良いか」職員みんなで話し合うことが必要で、園で取り組むべき課題を把握することができました。 |
| 講師 | 研修テーマ「あそびで育む生きる力について」(手遊び、歌遊び等の保育実技) |
|---|---|
リズムと表現の会 |
実際に体を動かして遊びながら、心と体をリラックスさせて楽しみ、こどもの気持ちになって他人と触れ合う心地良さや、つながる楽しさを体感しました。クラスの誰もが主役になる時間を持つことや、遊びの中でのこどもの表現を受け止める大人の役割の重要性を改めて感じました。年齢の発達段階を押さえた遊びの展開も教えていただき、明日からの教育保育にすぐに活かせる研修となりました。 |
 実際に触れ合って遊んで楽しみました。
実際に触れ合って遊んで楽しみました。
 笑顔があふれる研修の様子です。
笑顔があふれる研修の様子です。
| 講師 | 研修テーマ「身近な自然環境を生かした教育保育」 |
|---|---|
堺自然ふれあいの森 |
緑豊かな堺自然ふれあいの森で、身近な自然を使ってできる遊びや、自然と触れ合う時の注意事項等を学びました。音だけで仲間を探すゲームや葉っぱをつかったじゃんけんなど、ワクワクする遊びを通して、自然と触れ合う心地よさや、視点を少し変えることで、どの子も楽しめる活動になることを身をもって体験することができました。近年増えている、虫が苦手なこどもも楽しめるプラカップを使っての観察方法を実践し、これからの園庭あそびや散歩がより一層楽しくなる活動を沢山学ぶことができました。 |
 自分の好きな木にシールを貼りました。
自分の好きな木にシールを貼りました。
 虫を捕まえたり、テーマに沿った草花を集めました。
虫を捕まえたり、テーマに沿った草花を集めました。
 大きなバッタを捕まえました。
大きなバッタを捕まえました。
| 講師 | テーマ「園組織と協力体制作りについて」 |
|---|---|
大阪青山大学 |
保育者にもそれぞれに得意なところも苦手なところもあるのが当然で、教育保育はチームで行うという意識をみんなが持つことが大切だと学びました。そのためには職員間の対話が不可欠であり、園で大切にすることを確認していくと同時に、それぞれの保育者が大切にしていることも知っていく必要があると気づかされました。経験の浅い保育者が意見を出しやすい環境や、改善点だけを指摘するのではなく、評価できる点や良い点から話し合いを始めるなど、風通しの良い職場にするためのヒントを沢山いただき、今一度自分の職場について考える機会となりました。 |
| 講師 | 研修テーマ「職員が働きやすい職場環境づくりに向けたマネジメントについて」 |
|---|---|
関西福祉科学大学 |
若い世代を取り巻く社会情勢や環境の変化を教えていただき、価値観のチャンネルを管理職側が合わせる意識をもつことで、言葉のかけ方や伝え方が変わってくることや、「話をする」側から「話を聞く」側になることを心がけ話しやすい雰囲気を作っていく大切さを学びました。 |
| 講師 | 研修テーマ「ふれあい遊びや歌の保育実践」 |
|---|---|
ぬくぬくらんど主宰 |
講師の先生の優しい歌声に合わせて体を動かし、触れ合って遊ぶことの心地よさや気持ちがほぐれていくことを体感しました。小さいこどもにとっては同じ歌を繰り返して歌うことが安心感につながることや、少しのアレンジで乳児にも幼児にも楽しめる活動になることなどを学び、明日からの教育保育に活かせる気づきが沢山ありました。実際に絵本の読み聞かせもあり、こどもを温かく受け止めることの大切さや、絵本を通してこどもに伝えたいメッセージなど、教材選びの大切さも改めて感じる時間となりました。これからどんな楽しいことをこども達と展開していくか、明日からの教育保育が楽しくなる研修となりました。 |
 次々相手を変えてふれあいあそびをしました。
次々相手を変えてふれあいあそびをしました。
 紙皿を使った遊びのアイデアも学びました。
紙皿を使った遊びのアイデアも学びました。
救命講習会(普通3救命講習)

心肺蘇生は全員が手技を経験し、一刻も早い心肺蘇生の開始の重要性について学びます。実際に起こった時を想定し、チームを組んで心肺蘇生時に交代するタイミングの練習や、AEDの使い方についても学びました。心肺蘇生だけでなく、誤嚥の時の対応や、エピペンの取扱い等も学ぶことができ、こどもをあずかる施設の職員として、必ず全員が知っておきたい内容でした。実際に様々なケースを経験してこられた救急救命士の方のお話を聞き、命を預かる責任の重さに身が引き締まる思いでした。いざという時に正しい対応ができるよう、繰り返し訓練をし、身に着けていく大切さを感じた講習会でした。講習会を受けられた先生方が所属園で正しい知識を広めてくださることで、落ち着いて対応できる職員が増えていくことと思います。
 全員で心肺蘇生を行います。
全員で心肺蘇生を行います。
 チームを組んで心肺蘇生を行います。
チームを組んで心肺蘇生を行います。
このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 幼保支援課
電話番号:072-228-0283
ファクス:072-222-6997
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
このページの作成担当にメールを送る