乳岡古墳
更新日:2021年10月15日
指定区分
国指定史跡
指定名称
百舌鳥古墳群 いたすけ古墳・長塚古墳・収塚古墳・塚廻古墳・文珠塚古墳・丸保山古墳・乳岡古墳・御廟表塚古墳・ドンチャ山古墳・正楽寺山古墳・鏡塚古墳・善右ヱ門山古墳・銭塚古墳・グワショウ坊古墳・旗塚古墳・寺山南山古墳・七観音古墳・御廟山古墳内濠・ニサンザイ古墳内濠
内容
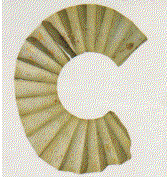 乳岡古墳出土車輪石(堺市博物館提供)
乳岡古墳出土車輪石(堺市博物館提供)
乳岡(ちのおか)古墳は、百舌鳥古墳群の最も南西に位置する前方部を南西に向けた前方後円墳で、百舌鳥古墳群では6番目の規模を持つ古墳です。前方部の大半は削られてしまい、3段に築かれた後円部のみが現存しています。周囲に巡っていた濠も埋められていますが、墳丘には葺石(ふきいし)があり、埴輪が立てられていました。昭和47年(1972年)には、埋葬施設の確認調査が行われています。その結果、後円部中央で粘土で覆われた長持形石棺(ながもちがたせっかん)が検出され、粘土からは車輪石(しゃりんせき)などの腕輪形石製品が出土しました。
乳岡古墳が築かれたのは、石棺の形や遺物から4世紀後半と考えられ、百舌鳥古墳群で最初に造られた大型前方後円墳です。
※ 石棺は埋め戻されて見ることができませんが、車輪石などの腕輪形石製品は堺市博物館で展示しています。
長持形石棺
蓋石・底石・4辺の側石の6枚の部材で構成され、蓋石がカマボコ状にふくらむ石製の棺。4世紀後半~5世紀後半にかけて、主要な古墳の棺として用いられる。
腕輪形石製品
碧玉(へきぎょく)で作られた腕飾り状の石製品。呪術的な「まつり」に用いられたものと考えられ、4世紀初頭~5世紀初頭の古墳に副葬品として納められる。
 東の空から見た乳岡古墳(堺市世界遺産課撮影)
東の空から見た乳岡古墳(堺市世界遺産課撮影)
所在地
堺市堺区石津町2丁620-1他
地図情報は「堺市e-地図帳」(外部リンク)をご覧ください。
所有者
堺市
特徴
前方後円墳
大きさ
墳丘長155メートル、後円部直径94メートル、同高14メートル
時代
古墳時代(4世紀後半)
指定年月日
昭和49年(1974年)1月23日 指定
平成26年(2014年)3月18日 統合・追加指定・名称変更
平成28年(2016年)3月 1日 追加指定
このページの作成担当
文化観光局 歴史遺産活用部 文化財課
電話番号:072-228-7198
ファクス:072-228-7228
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階
(文化財課分室)〒590-0156 堺市南区稲葉1丁3142
