テレビCMから読み解くジェンダー
更新日:2012年12月19日

ファシリテーター
吉田 清彦(よしだ きよひこ)
(コマーシャルの中の男女役割を問い直す会世話人)
コメンテーター
草川 衛(くさかわ まもる)
(社団法人ACジャパン専務理事)
谷岡 理香(たにおか りか)
(東海大学文学部広報メディア学科准教授)
CMは、限られた時間の中にたくさんのメッセージを盛り込んで作られています。そして社会や私たちのライフスタイルを映し出しているのがCMではないでしょうか?日々繰り返し流れるテレビCMはいちばん身近なメディアとして、無意識の内にさまざまな情報を刷り込んでいきます。分科会では、テレビCMにスポットを当て、ジエンダーの視点でCMに潜む問題点を考えました。まず、CMの制作・流通と新しいメディア発信について学びました。さらに、さまざまなCMをとおして参加者自らがメディア・リテラシー(情報を読み解く力)を身につけ、情報と上手に付き合う方法を学ぶ中で、より良い情報発信のあり方を模索しました。
広告を通した社会貢献

草川 衛
我々の組織、ACジャパンは何をやっているのかの説明をさせていただきながら、CMのお話をしたいと思います。ACはサントリーの社長であった佐治敬三さんがアメリカのACを勉強されて、1971年に関西で公共広告機構をつくりました。3年後に全国組織になって、社団法人公共広告機構(現ACジャパン)ができました。民間ボランティアの組織です。我々の考え方は、広告のもつ伝達力、説得機能を生かして、社会公共の福祉に貢献する。つまり広告というフレーム、仕組みの中で社会貢献ができないだろうかということです。社会生活者に対して、正しいことを訴える公共広告では、正しいメッセージ、正しいテーマの選び方、その表現の仕方がとても重要になります。正義の押しつけとか上からの説教にならないような配慮が必要です。そういうことがあって、初めて心を開いてメッセージを聞いてもらえるという状況になります。だから、最初に間違えていると、絶対我々の意図は届かないと考えて仕事をしております。
ただ、現実を考えますと、だれもお説教されたくないんです。それと、だれも自分は間違いないと思っていますので、公共広告というメッセージを我々が一生懸命投げかけても、それは自分じゃなくて、よその人へのメッセージだと思われて、無視されたり拒否されたりすることの方が圧倒的に多いです。それと、かたくなな心には、公共広告はなかなか届かない。だから、ターゲットは良心をもっている人だと考えています。
広告ができる最大の社会貢献活動ということを私たちの定義にしています。人の心を変えるというのは非常に難しい。心を変えて何かをしてもらうというのは非常に難しいけれども、まず人の心をどこまで優しくできるかの挑戦だと思います。かたくなな心を少し和らげて、そして私たちのメッセージが届いていくといういい循環が生まれて、その結果少しでも世の中がよくなっていくことに、広告が貢献できればということを追求するというのが私たちの仕事です。
皆さんが広告としてふだん見ていただいているものは商業広告です。生活者とともに経済の支えになってきましたが、強い表現で多くの引き付け、欲望を喚起するのが目的です。ですから、正義のキャッチボールという公共広告に対し、商業広告は受け手も送り手も、ともに虚構を楽しむ世界であるといえます。
広告におけるジェンダーの問題が、今日の主題ですけれども、やはりこういう機運、意識の高まりは進んでいます。以前は、見る側も寛容でしたし、また見えなかった部分もありました。問題含みの広告がかなり多かったんですが、今では意識はかなり高まってきたので、作り手も企画の段階ですごく注意を払うようになっています。
今日の主題でもありますが、その広告がどういう意味をもつのかということに作り手側が気がつくかどうかが、問題に対応ができるかどうかということにつながります。意識が低ければ低いほど問題を見過ごしてしまうので、何とか制作者側の意識を高めていくしかありません。
<CM上映>
「3丁目の夕陽」をモチーフにした広告では、抗議の電話や手紙をいただきました。それは、「男のくせに」という言い方、全体を通して父親の強さをあらわしていること、エンディングで子どもを寝かしつけている女性の役割のことなどでした。そういうふうに、作り手の意識の低さで、問題が起きるということがまだまだあります。
ジェンダーの視点をメディアに

谷岡 理香
草川さんからのCMのお話で、「だって女性がうちのことをしているのに、何でそれがだめなのかしら」と思っていらっしゃる方もいると思います。現実としてはそうですが、テレビで毎日毎日「ああ、いいCMね」と見ていると、「やっぱり女性がおうちのことをして普通よね」となってしまいます。しかし、この「普通」は時代によって変わってくるわけです。
私は大学で、「広告表現」という授業と、実際に学生がCMをつくる授業と、「女性とメディア」という、ジェンダーとメディアの気づきをもたせるような授業を中心に展開しています。
ACジャパンによる学生コンクールにも応募させていただいて、2年連続入選させていただきました。ただ、男の子も育児休業を取ろうという、稚拙ですがメッセージ性のとても強いものが入賞しませんでした。それがきっかけで調べてみたら、ACの役員の70数名が全員男性なんです。そういう方たちの価値観はどこにあるのかというときに、男に育休が必要という気づきも、ひょっとしたらないかもしれない。選ぶ側にもそういった人を入れていただきたいと思いました。
私は、今は大学の教員をしていますが、もともとは大学を卒業して、ずっと放送局の中で仕事をしてきました。最初は正社員として。でも、均等法前なので、女は結婚したら辞めてねという形で体よく追い出されてしまって、その後はフリーランスで、主にNHKの中でニュースの仕事をしていました。ジェンダーとメディアに一番大きく気づいたのは、NHKの中で仕事をしていたときです。特にコマーシャリズムとは関係がない報道の分野において、しかも公共放送で、自分がアナウンサーとして、あるいは取材者として仕事をしていたときに、どうもデスクや、その当時の男性たちの価値観がちがうというところに気づき始めました。私が大事だと思うテーマでも、それをニュースに選ばない人たちがいるわけです。だから、出なかったニュースは何なのか、出た女はどんな女か、出なかった女はどんな女か、この問題は広告の世界にもつながっていくと思います。そこからジェンダーとメディアについて勉強するようになりました。
95年の国連の第4回世界女性会議で、メディアは、とても社会に与える影響が大きい。だからこそその中で描かれる女性像は多様であるべきである。それから、メディアの中にたくさんの女性が入っていくべきである。さらに、決定権のあるところにいるべきであるということが挙げられています。
<男女共同参画に関する学生制作のCM上映>
作り手の側のジェンダーバランスの悪さ

吉田 清彦
作り手の側のジェンダーバランスの悪さの一例として、放送局で働く女性の比率を見ると、NHKの全従業員に占める女性の割合は、2006年で11.5%。男性9人と女性1人でつくっていることになります。どんなニュースを優先的に流すかを決める立場にある管理職と専門職に占める女性の割合は、わずか2.9%。日本政府は国連の勧告を受けて、あらゆる分野での決定権をもつ立場の女性の数を2020年までに30%にすることを目標にしていますが、NHKはいまだ遠しという感じです。ですから、視聴者の側がどんどん要求を出すことが大切です。それと、メディアの中で頑張っている女性を応援することも大事です。ちなみに、民放の女性比率は、NHKより少し高くて21%。女性のアナウンサーが増えている感じがしますが、全体では男性が8割で女性は2割。決定権をもつ立場の女性は9.7%、まだ1割に届かないのが現状です。ただ、1割はいるので、その人をもっと応援することが大事です。
今からメディアリテラシーのワークショップを行っていきますが、日本ではFCTという市民グループが、カナダのオンタリオ州の取り組みを基本にして、メディアリテラシーという言葉を普及させました。メディアリテラシーの目的は、FCTのメンバーの方が「メディア社会に生きていることを意識化する」ことと再定義しています。
「テレビは空気のようなものだ」と言った人がいます。あるのが当たり前、なければ困ると。それだけ影響力が大きいのです。そのようなメディアからの情報を、クリティカルに、つまり、批判的ではなく、批評的に分析して、評価する力を獲得する。そして、クリティカルな評価や判断に基づいて、自分自身の表現を含む、新しいコミュニケーションをつくり出す。これがリテラシーです。
《ワークショップ》
90年代初頭のCMを見ての参加者の感想
参加者
高度経済成長の時代に、男性が企業戦士と言われた時代がありましたが、それがまだ、この時代に残っている雰囲気があると感じました。男女の固定的な役割分担というのが描かれているものもありました。幾つかのCMについては完全に女性をべっ視していると強い意見もありました。
また、商品そのものよりも、CMによって印象づけられるという部分が大きいので、CMの役割というのは、私たちにいつもすり込まれて、非常に大切なものであるということを再認識しました。
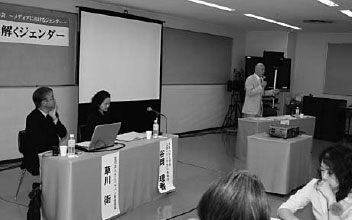
参加者
このCMが流れた当時は、これを余り不思議に思わない、当たり前に思った方々が多かったのではないか。もともと基本法以前ですし、男女共同参画の視点というものがなかったのではないかと。
それから、男の人が非常に喜ぶ映像が多かったと思う。受け手というのは、当然男女あるべきなんですけれども、男性しか見ていないような内容になっているものが多くありました。
それと商品そのものが、別に女性の裸と何ら関係がないようなものでも、それを不思議に思わずに、とにかく女性の裸を多く登場させて、今の私たちから見れば非常に腹立たしい、失礼な映像が平気で流れていたことに驚きを感じました。非常に衝撃的な映像ばかりだったという感想です。
参加者
男性が、家事とかに携わった表現をしていかないといけないという声が強くあがってきた時代だったと思います。ですから、洗濯のCMなどは無理に男性を起用したような、今とちがって自然さがなかったといった意見が出ました。
参加者
あるCMでは、一見、女性にとても便利になりましたと言っているようですが、結局その根底にあるのは、子育ても仕事も家事も、全部女性なんですよ、そのあなたたちをもう少し便利にしてあげましょうという、そういうお仕着せのメッセージが受け取れました。
2001年栄養ドリンク・紙おむつをテーマとしたCM、2009年ACジャパンのCMを見ての参加者の感想
ACのCMでは、おとなのやることを子どもが見て育つということで、世代間のメッセージはよく伝わるかなと。ただ、男性だけが出ていたことと、今風のだらしない服装だけで悪いことをするという決めつけ感があるという意見が出ました。また、しかることから子どもが育っていく、おとなの毅然とした態度が必要であるというメッセージはよく伝わったと思います。
おむつのCMでは、これは息子ではない、恐らく息子ならもっと乱暴な言葉遣いになるのではないかという声が出ました。男が男を介護しているという、CMとしては新しさがあるのかなという気がしました。
参加者
ACのCMでは、悪いことをするのは男の子、しかるのは母親という決めつけがあるという意見が出ました。それから、子どもから急におとなになっていて、その過程で教育はなかったのかという意見も出ました。
栄養ドリンクのCMですが、女性の姿を身につまされるように見ました。夫さんは多分スーツを脱いで、ふんぞり返ってご飯が出てくるのを待つんだろうという展開が予想されました。でも、夫が、妻も疲れているんだということにやっと気づいてくれたかという印象ももちました。
それからおむつのCMですが、男は男が介護するのがいい、そして息子ではないんだという設定で、最後の、おしっこのことが言えたとか、そういうのも女性の介護士だったら言えないことだけど、同性だからああいう言葉が出たんだろうということから、やはり男性は男性が介護すべきで、女性は女性に介護されたいと思っているのでは、という意見が出ました。
参加者
まずACのCMですけれども、おうちで、家庭でしつけは必要だということですけれども、その家庭教育が母親、もしくはおばあちゃんであるということから、母親がすべきものだということがあるのではないかと、そこがちょっとおかしいという意見が出ました。
それと栄養ドリンクのCMにつきましては、男性のスーツはばりっとしているが女性の方はよれよれに思えたと。そういったところからも疲れている感が出ていた。あと、自転車ということで、近くで非正規のパートのようで、またかつ、仕事プラスアルファの家事をしないといけないということが描かれていて、やっぱり男性の視点というのが感じられたという意見がありました。
ほかにはCMのつくり方に、10年前よりもぎこちなさはなくなってきているのではないかなという意見もありました。
参加者
リハビリパンツのCMで、これは親子だというイメージでとらえています。全く女性が出てこないので、男性が男性を介護しているんだというアピールが強過ぎるイメージを受けました。
参加者
リハビリパンツのCMでは、親子であるという意見と、親子じゃなくて利用者とへルパーという、そういう意見に分かれました。ただ、そういう問題は受ける側としていいと私は思います。それに関して、これからは、寝たきりゼロにするために、そういう紙おむつが出たんだよ、介護はそんなに大変じゃないんだよということをアピールしたいのだと思いました。
ACのCMでは、きちんとしかろう、ちゃんとしかろうという言葉がとても印象的でした。ただ、青年役は、もうちょっと悪ぶって、もっとだらしなくしてもいいかなと思いました。
栄養ドリンクのCMは、男女のスーツ姿の夫婦ということで、せりふがなくて物悲しいという意見もありましたけれども、遠くから見つめる夫の視線が、優しさとか思いやりを感じる視線で、すごくよかったという意見と、働いている妻が疲れているのを夫が見守っているという、その優しさを感じたということで、これから頑張っていこうとも取れました。
参加者
栄養ドリンクのCMでは、かごの中に買い物した物が入っているということなどを考えると、その女性がこれから家に帰ってご飯の支度をするのかなと。それを町の雑踏で、ちょっと妻の姿をかいま見た男性が、この人が家に帰る時間帯ではないように感じました。もしかしたら、企業から企業に渡る間に、ちょっと雑踏の中に妻の姿を見て、ああ疲れているなという、このとらえ方そのものは時代をよく反映して、少し男性が家事なり、女性の働きに視線をやったという点で、ちょっとほっとするという発言もありました。
それから、三つのCMに言えることですが、すべてのナレーションが男性によって行われていて、ACの最後の部分で、優しい、やわらかいというイメージのとらえ方で、女性が出てきて男の子の頭をなでながら、そういうナレーションをしているという点については、やはり男性のナレーション、声の力と、女性のやわらかさ、優しさみたいなところが、暗に作り手にも計算があるのかもしれないという発言がありました。
講評
吉田 清彦
最後の指摘は鋭くて、我々が20数年見続けているなかでも、説得的なフレーズは男性が話すことが多いです。
今、多様な意見が出ました。どれが正しいかというのを決めるのではなく、多様な意見を出しながら調整していくというのが、これからの民主主義のルールです。
草川 衛
ACの広告についていろいろご意見をいただきまして、本当にありがとうございました。私だけ参考になってもだめですので、案を考える人、それからそれを選ぶ人にもこのことを伝えていかなければいけないなと感じました。
谷岡 理香
こういう場所に積極的に自らの意思で来られた方は意識も高く、また、人生経験が豊富だと、読み取る能力が高いと思います。学生がさっきの栄養ドリンクのCMを見ても、こういう優しいパートナーが欲しいとかしか読み取れないかもしれません。
それから皆さんが読み取られたものも、作り手がそこまで意識してなかったのにということもあれば、よくそこまでということも、それは作った人に聞いてみないとわからないわけですね。でも、作品というものは、作り手の意識を超えて、受け手側のこれまでの人生の価値観とか、世代とか、育った環境によって、能動的に解釈しますので、必ずしも作り手の思いどおりに受け手は解釈しないので、多様な読み取りがあっていいと思います。
そして、多様性というときに、今なぜ女性の問題を取り上げるかというと、マイノリティの代表格として女性がいる。でも私たちの後ろに、もっとマイノリティの方々がいます。在日の方や外国人の方は、まだほとんど出てこない。もっとマイノリティの方々に向けての広告もあっていいと思いました。多様性というとき、寝たきりになっても私たちは、だれかのサポートを受ければ、ちゃんと自分の意思で生きいける社会という広告もお願いしたいと思いました。
「今後のテレビCMのあり方について」参加者意見
参加者
CMは変わったかという点については、実際変わったと思う。性的な描写はあるけれど減ってきた。男性が家事をする姿も少しは自然に表現されるようになった。頑張れ、頑張れのCMから、頑張り過ぎなくていいよとか、おむつのシーンでも、ゆっくりでいいよというような、優しいメッセージを送る内容になってきているということ。それから、ストーリー性のあるCMに変わってきた。商品を最初に出さずに最後に出すような、ドラマを見ているようなCMなど、なかなか工夫をしてきているという意見が出ました。
今後メディアとどう向き合って行ったらいいかということでは、これからは問題意識をもってCMを見ないといけないという意見が出ました。特に腹の立つCMの商品は絶対買わない、これも一つかなと。特にACさんには、これからもっと学べるCMをたくさん作っていただきたいというご意見も出ました。質問ですが、CMに対する意見はどこに言ったらいいんでしょうか。
草川 衛
JAROという組織があります。苦情、ご意見を承る組織です。
参加者
JAROや民放連盟でも決定権をもつ人がまだ男性ばかりで、根本的には、変わってないのではないかと。男女共同参画といっても、決定の場に女性が少ないということで、根本的な解決になっていないのではないかという意見がありました。
参加者
CMは変わってきていると。家族の形態が変わってきているので、CMに登場する家族も、多様性をもった人間関係を盛り込んだものにしていただきたいという要望もありました。CMは社会の縮図と考えられますので、本当に多様性をもって作っていただきたい。男女のバランス、世代間のバランス、そういったものをもって作っていただきたいという話もありました。
受け手の方の立場としても、テレビに出てきたものをうのみにせずに、批評をするような気持ちももってCMを見ていきたいなと思いました。質問ですが、ACの広告に、一般の人が企画をお願いすることはできますか。
草川 衛
残念ながら現状ではできません。
吉田 清彦
今、アメリカのケーブルテレビと同じように、日本の政府も、市民がつくった作品を流せるチャンネルを保障するような仕組みをつくろうとしています。
参加者
今後は、男女の役割が固定されなくて、男性とか女性がぼやけたような、そういうものがあってもよいのではないかという意見がありました。
このままではテレビは廃れていくのではないか、CMというと、テレビCMというのを一番大きくとらえますが、中高齢者がいなくなれば、デジタル化されたときに、もうテレビは要らないという世代が今後増えて、テレビCMでは伝わっていかないのではないかという意見もありました。
講評
吉田 清彦
人を出すとどうしても性別役割が出てしまうので、先ほどのパスタのCMのように、人を出さないで商品をしっかり宣伝するというようなCMが20年くらいから増えてきています。
あと、若い方がテレビを見なくなるのではないかということですが、視聴時間は減っていますが、今、携帯電話でもテレビは見られますので、若者がテレビをまったく見なくなるということはないと思います。
メディアリテラシーの究極は自ら発信すること
谷岡 理香
草川さん、ACでは、学生たちはつくれるのに、なぜ市民は窓口がないのでしょう。市民グループからもぜひ募りましょう。
私は批判されて人は育つと思っています。私は学生たちに、やっぱり放送の世界はおもしろい、広告の世界もおもしろいと言って送り出したいと思っています。でも、メディアは批判されるべき存在でもある。なぜならば社会的に責任があるからである。そこにジェンダーの視点が大事だと言っています。
ものを作るってとてもおもしろいんです。自分が伝えたいことを社会に発信できるのは、すばらしいことだと思うんですね。メディアリテラシーの究極は自ら発信ですから、ジェンダーの気づきを大事にしながら、発信をぜひ皆さんにもしていただきたいと思います。
<男女共同参画に関する学生制作のCM上映>
今、世の中は、とても複雑になってきています。いいか悪いかだけではわからない時代になっています。だからこそ、メディアが社会に何を果たせるかというのは重要な役割で、21世紀は好むと好まざるとにかかわらず、メディア社会です。特にインターネットが革命のように起こってきた後は。だからメディアリテラシーが重要で、多様性を認め合うということは、少数者を認めるということなので、男女のちがいだけではなくて、人種や国籍、あるいは障害の有る無しに関わらず、そして認知症になっても生きていける社会のために、メディアは何ができるのかということをお互いに考えていきたいと思います。
表現の受け取り方とクレーム
草川 衛
ACジャパンの思いは、本当に世の中のためになるようなことを進めていきたいということ。表現の受け取り方に関しては、皆さんそれぞれちがうと思います。我々の意図する一番大きいところを捉えていただき、それから部分的な問題点も発見していただきたい。公正な見方、広い心で見ていただければと思います。頑張りますので宜しくお願いします。
市民がリードする取り組みを
吉田 清彦
北京の世界女性会議で採択された行動綱領では人権とメディアはそれぞれ別枠なんですが、日本の行動計画では「女性の人権とメディア」といっしょになっていて、日本はメディアに対する取り組みでは、恐らく世界で一番遅れているのではないかと思います。
皆さんはこれから、それぞれのもち場に帰って、行政や地域や家庭で、メディアに対する取り組みをいろいろなかたちで行なってください。メディアは本当に空気のように大事です。ですからそれを制作者任せ、あるいは行政任せにせずに、市民がリードするかたちで私たちにとって快適なメディア環境をぜひつくり出していきましょう。
このページの作成担当
市民人権局 ダイバーシティ推進部 ダイバーシティ企画課
電話番号:072-228-7159
ファクス:072-228-8070
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階
このページの作成担当にメールを送る