堺市国民保護計画概要版
更新日:2012年12月19日
堺市国民保護計画をご存知ですか?
平成19年 堺市
目次
1 「堺市国民保護計画」とは?
計画作成の根拠
なぜ、「堺市国民保護計画」を作成する必要があったのですか?
平成16年6月、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」が成立し、同年9月施行されました。
この法律は、我が国に対して外部からの武力攻撃などが発生したり、予測されたりする事態において、それらから国民の生命、身体及び財産を保護し、そういった攻撃による国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃等災害への対処に関する措置などを定めたものです。
これらの措置を実施していくため、国民保護法の中で、市町村は計画の作成を義務付けられております。そこで、本市においても、この法律の規定に基づいて、平成19年2月に「堺市国民保護計画」を作成いたしました。
保護の対象者
この計画によって保護されるのは、堺市内に住む人だけなのでしょうか?
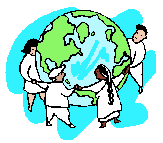
この計画では、市域内にいる住民はもちろんですが、それ以外に武力攻撃等事態が発生した際に、通勤、通学、旅行などで市域に滞在する人や、他の市町村から市域に避難してきた人も保護の対象としています。
また、これらの人については、国籍を問いません。そこで、この計画において、保護の対象となるこれらの人を「市民等」と呼ぶこととしています。
計画が対象とする事態
「堺市国民保護計画」は、どんな事態を対象としているのですか?
国が定めた「国民の保護に関する基本指針」では、武力攻撃事態については4類型、緊急対処事態については4事態例が想定されています。この計画においても、これら全てを対象とし、その類型・事態例に応じた国民(緊急対処)保護措置を実施していきます。
1 武力攻撃事態として想定される4類型
武力攻撃とは、我が国に対する外部からの武力攻撃をいい、武力攻撃事態とは武力攻撃が発生した事態又は発生する明白な危険が切迫している事態をいい、武力攻撃予測事態とは武力攻撃事態には至っていないが、事態が切迫し、武力攻撃が予測される事態をいいます。上記の「基本指針」においては、武力攻撃事態として、次に掲げる4類型が示されています。
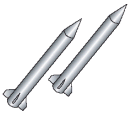
(1) 地上部隊が上陸する攻撃
(2) ゲリラや特殊部隊による攻撃
(3) 弾道ミサイルによる攻撃
(4) 航空機による攻撃
2 緊急対処事態として想定される4事態例
緊急対処事態とは、武力攻撃の手段(たとえば、著しい破壊力をもった爆弾の使用や生物剤・化学剤の散布など)に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又はそういった危険が切迫している事態で、国家として緊急に対処することが必要なものをいいます。上記の「基本指針」においては、緊急対処事態として、次のような4事態例が示されています。
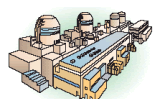
攻撃対象施設等による分類
(1) 原子力事業所や石油コンビナート等の爆破など
(2) 大規模集客施設やターミナル駅等の爆破など
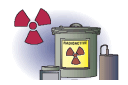
攻撃手段による分類
(3) 放射性物質を混入させた爆弾等による放射能の拡散や炭疽菌・サリン等の大量散布など
(4) 航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロなど
2 計画の内容
市が実施する措置
市は、これらの武力攻撃等事態が起こったとき、どのような措置を行うのですか?
万が一、前ページにある武力攻撃事態や緊急対処事態が起こったとき、市では、「避難」「救援」「武力攻撃等による災害への対処」が、担うべき重要な役割の3本柱となります。具体的に行う措置としては、下記のようなものがあります。
1 警報の伝達・通知

武力攻撃等から国民の生命や身体、財産を保護するために緊急の必要があるとき、国は警報を発令します。国が発令した警報の通知を府から受けたとき、市は直ちに、防災行政無線、広報車、電話、ファクシミリ、インターネット、携帯電話への一斉メールなどのあらゆる手段を活用して、市民等や関係団体、関係機関などへ警報を伝達・通知します。各世帯等への伝達については、消防と連携し、自主防災組織や自治会等の自発的な協力を得るなどして行います。

〈1〉屋内にいる場合
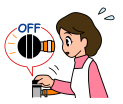
- ドアや窓を全部閉めましょう。
- ガス、水道、換気扇を止めましょう。
- ドア、壁、窓ガラスから離れて座りましょう。
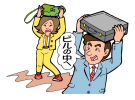
〈2〉屋外にいる場合
- 近くの頑丈な建物や地下街など、屋内に避難しましょう。
- 自家用車などを運転している方は、できる限り道路外の場所に車を止めてください。やむを得ず道路において避難するときは、道路の左側端に沿ってキーを付けたまま駐車するなど、緊急通行車両の通行の妨害とならないようにしてください。
※テレビやラジオなど、各種情報に耳を傾け、落ち着いて情報収集に努めましょう。
2 避難誘導
国は、警報を発令し住民の避難が必要であると判断したとき、避難の必要な地域と避難先を大阪府へ指示します。
避難の指示の内容としては、屋内への避難、校区内の避難所への避難、市域や府域を超えた遠方への避難など、自然災害の場合と違ってさまざまなパターンが考えられます。市では、府からの避難の指示を受けたときは、この指示に基づいて、直ちに避難実施要領(避難先や集合場所、避難経路など)を定め、その内容をすみやかに市民等や関係団体に伝達します。
この避難実施要領にしたがって、市職員は、消防、警察、海上保安部、自衛隊などの関係機関の協力、また市民やボランティアの自発的な協力を得て、避難住民を誘導します。
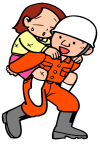
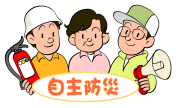
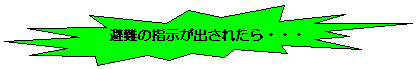
自宅から避難所へ避難する場合は、以下のことに留意しましょう。
- ガスの元栓を閉め、コンセントを抜いておきましょう。冷蔵庫のコンセントは挿したままにしておきましょう。
- 頑丈な靴、長ズボン、長袖シャツ、帽子などを着用し、非常持出品(次ページを参考にしてください。)を持参しましょう。
- パスポートや運転免許証など、身分を証明できるものを携行しましょう。
- 家の戸締りをしましょう。
- 近所の人に声をかけましょう。
※みなさんの安全を守るための指示です。避難の経路や手段について指示にしたがい、落ち着いて行動しましょう。
一次非常持出品チェックリスト
一次持出品とは?
被災直後、被災の際に持ち出す必要最小限の備えで、非常時の最初の1日間をしのぐための物品です。
基本品目~あらゆる家庭に共通して必要~

- 非常持出袋
食料関係
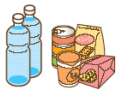
- 缶入り乾パン
- 飲料水(500ミリリットル)
生活用品
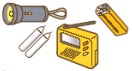
- 懐中電灯
- ローソク・ライター
- 携帯ラジオ
- 万能ばさみ
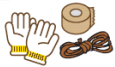
- 軍手、手袋
- ロープ
- ガムテープ
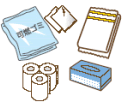
- タオル
- ポリ袋
- ウェットティッシュ
- トイレットペーパー
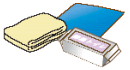
- レジャーシート(2畳)
- ブランケット
- 簡易トイレ
救急用品
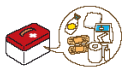
- 救急袋
- (毛抜き・消毒薬・脱脂綿・ガーゼ・ばんそうこう・包帯・三角巾・マスク等)
![]()
- 常備薬
その他
![]()
- 現金(小銭も)
- 筆記用具・油性マジック
以下のものは、上記の基本品目に加え、それぞれの状況に応じて持ち出すものです。
必需品・貴重品

- 現金(予備費)メガネ・コンタクトレンズ
- 携帯電話
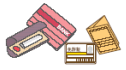
- 預金通帳・印鑑
- 身分証明書類(健康保険証、免許証、パスポート、外国人登録証、住民票、証書類等)
高齢者用品
![]()
- 看護用品
- 持病薬
![]()
- 高齢者手帳
- メガネ(老眼鏡)
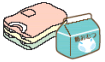
- 紙おむつ
- 着替え
女性用品

- 生理用品(ナプキン、おりものシート)

- 化粧品
- ヘアケア用品(ブラシ、鏡等)
- ホイッスル付ライト
赤ちゃん用品

- 粉ミルク、哺乳瓶、離乳食、スプーン
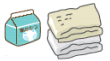
- 紙おむつ、おしりふき
- ガーゼ、洗浄綿
- バスタオル、着替え

- 玩具
- ベビーカー
- 母子手帳
3 救援
市は、避難先地域となった場合には、避難住民を受け入れる避難所の開設や食品・飲料水・寝具などの供給、医療の提供などの救援の措置を行います。
救援の初期段階においては、衣・食・住の基本的な救援を重視し、長期化する場合は、応急仮設住宅の建設や公営住宅等の供与、福利厚生の充実、子どもたちの教育環境の整備など、避難住民の生活基盤を安定させるのための救援を重視して行います。また、武力攻撃等災害による負傷者などが多い場合は、避難所に臨時救護所を開設するなど、状況の特性に応じた救援の実施に努めます。


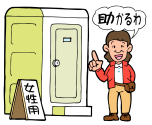
また、救援を行うため必要があるときには、市では、医薬品や食品などの特定物資の所有者に対する物資の売り渡しの要請や収用、施設供与のための土地や家屋の使用などを、定められた手続を取った上で行います。
4 安否情報の収集
市では、避難住民や、武力攻撃等災害により死亡したり、負傷した人の安否情報を収集します。安否情報として収集する対象者は、避難が必要な地域の市民等であって、指定された避難所に避難している人や要援護者等で、施設にいる人と武力攻撃等災害により死亡又は負傷した人を主対象としており、帰宅困難者や親戚・知人宅等への避難者は原則として含まないものとしています。
安否情報の収集は、定められた様式にしたがい必要事項を可能な範囲で、警察、消防、病院等の関係機関、避難所の管理者などの協力を得て実施します。
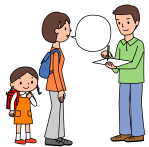
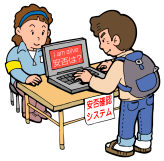
5 武力攻撃等災害への対処
市では、武力攻撃等による災害が発生したり、まさに発生しようとしている場合において、緊急の必要があるときには、消防をはじめとする関係機関と連携して、目前の危険を一時的に避けるための退避の指示や警戒区域の設定、消火・救助・救急活動など、応急措置等を実施します。
市では、退避の指示や警戒区域の設定を行ったときには、防災行政無線や広報車などを使って速やかに市民等に伝達します。また、放送事業者に対してその内容を連絡します。


市では、避難先地域において良好な衛生状態を保ったり、そこで過ごす人たちが心身双方の健康状態を保てるよう、必要な福祉サービスの実施に努めます。また、武力攻撃等に伴う被災状況について情報を収集し、市民等に対して正確かつ積極的な情報提供に努めます。


6 石油コンビナート等地域における災害対処
石油コンビナートを抱える市では、周辺地域を含むこの地域で武力攻撃等による災害が発生した場合、より安全性に配慮し、地域特性に合った適切な対処を行う必要があります。そこで、市では、防災体制について定めている「大阪府石油コンビナート等防災計画」との連携を保ちながら、周辺の市民等の避難など、必要な措置を実施します。
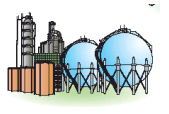
措置実施の際の留意事項
国民(緊急対処)保護措置を実施していく上で、どんなことに留意しているのですか?
もしも武力攻撃等事態が起こった場合には、市では、国民保護法やこの計画に基づいて、これらの措置を的確かつ迅速に実施する必要がありますが、その際には、次のような項目に、特に留意しています。
1 基本的人権の尊重
措置の実施にあたっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利を最大限に尊重します。救援等の措置において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最小限のものに限り、公正かつ適正な手続の下に行います。
2 市民等の権利利益の迅速な救済
これらの措置の実施に伴う損失補償、措置に係る不服申し立てや訴訟その他市民等の権利・利益の救済に係る手続きを、できる限り迅速に処理するよう努めます。
3 高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、外国人等への配慮及び国際人道法の的確な実施
措置の実施にあたっては、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、外国人その他特に配慮を要する人の個性や生活状況に応じた、きめ細かな保護について留意します。
また、この計画の保護の対象者の国籍は問わないことを認識し、国際的な武力紛争に適用される国際人道法を的確に実施します。さらに、男女共同参画の視点に基づく計画の推進に努めます。
4 措置の実施に従事する人などの安全の確保
これらの措置の実施に従事する人や要請に応じて措置の実施に協力する人の安全の確保には十分配慮します。
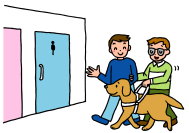
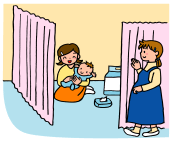
3 市民やボランティアの協力
市民やボランティアに期待されること
この計画の中で、市民やボランティアにはどのようなことが期待されているのですか?
阪神・淡路大震災では、大規模災害時の初動対応における自主防災組織やボランティアの役割の重要性が指摘されました。こうした自主的な防災活動は、この「堺市国民保護計画」の推進においても、住民の避難や被災者の救助などの局面において、十分活かされるべき大切なことです。
自主的な防災組織やボランティアなどによる市民等の協力としては、次のような活動があります。
〈1〉住民の避難や被災者の救援の援助
〈2〉消火活動、負傷者の搬送又は被災者の救助の援助
〈3〉保健衛生の確保に関する措置の援助
〈4〉避難に関する訓練の参加



中でも、災害時要援護者への警報など情報伝達や避難誘導において、重要な役割を果たすことが期待されています。
たとえば、自ら避難することが困難な在宅者の避難誘導について、市は、事前に把握した情報等に基づき、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、介護保険事業関係者、障がい者団体等や、自主防災組織、自治会等の地域住民の自発的な協力を得ながら、実施します。
地域で取り組む災害時要援護者対策
1 災害時要援護者の身になって防災環境の点検をしましょう
- 避難路は車椅子でも通れるか。
- 放置自転車などの障害物はないか。
- 目や耳の不自由な人や、外国人向けの警報や非難の伝達が確立されているか。
2 災害時要援護者の防災能力アップを支援しましょう
- 災害時要援護者の参加できる防災知識や講習会の開催。
3 地域での協力・支援体制を、具体的に決めておきましょう
日常、非常時、被災後の支援方法や体制を明確にしておきましょう。
(例)
- 日常の連絡役
- 非常時の救援者
- 救援者不在の場合の救援者
- 被災後の支援者
4 地域住民の意識の向上
- 地域社会で共生していく住民同士として、支援活動を推進するようにしましょう。
自発的な協力
市民やボランティアの協力は、法律で義務付けられているのですか?
措置の実施のため必要があるときは、国民保護法の規定により、市民やボランティアに対し、必要な援助について協力を要請しますが、この場合の協力は、自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請が強制されるようなことがあってはなりません。
また、市では避難や救援などにおいて市民等の自発的協力が得られるよう、平素から広報・啓発等に努めます。

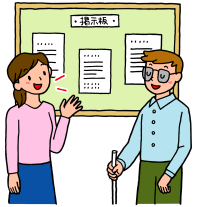
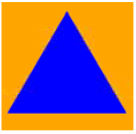
上記のマークは、1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(第一追加議定書)の中で定められている国際的な特殊標章で、国民保護措置に関係する仕事や協力を行う人、そしてそれらに使用される場所や車両、船舶、航空機等を見分けるために使用することができます。
堺市国民保護計画 概要版
平成19年7月 発行
編集・発行 堺市総務局危機管理室
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
電話:072-228-7605
堺市行政資料番号 1-16-07-0145
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
