ウィキペディアタウン in さかい(平成30年2月11日)を開催しました。
更新日:2018年3月9日
平成30年2月11日(日曜日)、中央図書館で「ウィキペディアタウン in さかい」を開催しました。昨年に続き2回目の開催です。
Wikipedia(ウィキペディア)は誰でも編集できるインターネット上の百科事典です。堺を歩いて、歴史や文化を学んだあと、図書館資料で調べて、みんなでウィキペディアの記事を作成しました。
今年のテーマは堺事件
今回は郷土資料展「堺事件150年」の関連イベントです。
旧暦の慶応4年(1868年)2月15日、堺において土佐藩士によるフランス兵士殺傷事件が起こりました。直後に事件の責任をとって土佐藩士は堺の妙国寺で切腹。多額の賠償金を支払うことになりました。この「堺事件」が起きて、今年が150年になります。
時代の転換期に起こった「堺事件」は歴史小説にこそ多く取り上げられてきたものの、わかっていないことが多くあります。色々な立場の人物が複雑にからむ「堺事件」を様々な角度から見ていただけるように、展示とイベントを企画しました。
まずはまちあるきに出発!
10時に南海堺駅集合。寒いけれど、よく晴れました。
まずは、まちあるきです。二班にわかれて、堺事件の発生した堺旧港あたりを歩きます。案内は、NPO法人堺観光ボランティア協会のベテランガイド呉竹さんと野澤さん。午後からの編集作業に関わる、土佐十一烈士記念碑、神明神社、堺台場跡、龍神堂をガイドいただきます。
土佐十一烈士記念碑。堺事件の発生場所です。ガイドさんの説明も午後からの作業の手がかりになるので、しっかりメモ!
神明神社は「堺のお伊勢さん」と呼ばれ親しまれています。案内板も撮影しておき、午後からの作業に備えます。
幕末に外国船の来航に備えるため築かれた台場は、のちに大浜公園になりました。一部の石垣が今も残りますが、あまり知られていません。
龍神堂です。小さな敷地の中に白龍大神をはじめ、たくさんの祭神が祀られています。
ポイントを効率よく歩き、二班とも時間どおりに堺駅に帰ってきました。ガイドさんの時間管理、さすがです!
いったん解散してそれぞれ昼食をとったあと、中央図書館に集合します。
展示解説を聞いてさらに知識を深めます
午後は、まず郷土資料展「堺事件150年」の見学です。展示を担当した職員の解説を聞きながら、じっくり見ていただきます。編集で使えそうなネタや画像がチェックできたでしょうか。
作業の前にレクチャーを聞き、しっかり勉強します
それぞれ興味をもった項目を選んで「堺事件」、「神明神社」、「堺台場跡」、「龍神堂」の四つの班にわかれます。「堺事件」は既にウィキペディアに項目がありますので、記事の編集になります。他の項目は新規に記事を作成します。どちらも、それなりの難しさがあります。
記事を作成する前にレクチャーを聞きます。図書館から地域情報の調べ方について、オープンデータ京都実践会の青木さんからウィキペディアについて、オープンデータ京都実践会のMiyaさんからウィキペディアの編集について。3本、計1時間のレクチャーです。
図書館でさがせる地域の情報について学びます
ウィキペディアタウンでどんなことをするのか、参加するとどんなメリットがあるのか学びます
ウィキペディアについて知り、編集する際に気をつけることなどを学びます
今回、図書館レクチャーで大きくとりあげたデジタルアーカイブでは、図書館所蔵の絵図などの画像をたくさん見ることができます。記事内にリンクを貼っておけば、ワンクリックで関連する画像を見ることができます。
いよいよ記事の作成を開始します
あまり信用できないと思われがちなウィキペディアですが、Miyaさんの講義にもありましたように、ウィキペディアは何かを調べるときの入口として、とても便利なものです。信頼できる参考文献に基づき記述された記事は大変価値がありますし、参考文献が書かれていれば、誰もが記事を検証できます。堺に関する情報をたくさんもっている堺市立図書館の資料を使って、信頼できる記事を書いて発信することをめざします。
さて、いよいよ作業です。
ウィキペディアでは、資料やインタ―ネット情報の単なる引き写しは著作権の関係上認められません。自分の意見を書いたり、偏った観点だけを書くことも認められません。
教わったことに注意しながら、考えたり、調べたり、議論したり、記事を書いたり、写真をアップロードしたり。作業時間は二時間しかありません。
「堺事件」は既に項目がありますが、追加できそうな記述がたくさんあります。図書館が作成したブックリストをもとに「堺事件が登場する小説」などもアップすることになりました。
「神明神社」は堺市内に同名の神社があるため、注意が必要です。この班では図書館が準備した資料ではなく、ガイドさんが持っておられた神明神社略記が大活躍でした。
「堺台場跡」班には写真が得意な地元の方と、パソコンに強い方の混合チームとなりました。当日の写真以外にも菖蒲の時期に撮影した写真や、デジタルアーカイブの画像リンクもアップすることになりました。
「龍神堂」班は閲覧室からさらに資料を探してきて、わからない部分を追及。紙の資料だけでなく、デジタルアーカイブをはじめとする図書館の公開するデジタル資料もたくさん使うことになりました。関連する項目「旭館」も書いてみることになったようです。
成果発表です!
二時間で容赦なくタイムアウト!各班、成果発表を行います。作成したウィキペディアの記事をスクリーンにうつして、それぞれ記事にどう関わったかを発表いただきました。
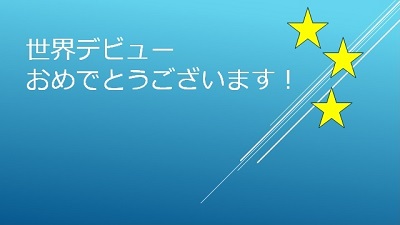
おつかれさまでした!時間内に四つの記事がウィキペディアにあがりました。
フェイクニュースが話題となる昨今ですが、情報の発信される過程を知ることは、信頼できる情報を見分けることができる大きな強みとなります。
ウィキペディアの記事はいったん投稿したあとも、いつでも誰でも加筆や書き換えができます。今回作成した記事もどんどん編集されています。編集履歴もすべて確認することができます。信頼できる情報を発信し、共有しようとこころざすウィキペディアの世界の一端がのぞけたのではないでしょうか。
みなさん、とても良い笑顔です!
