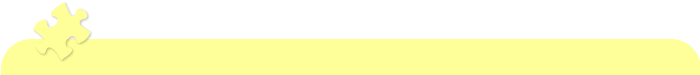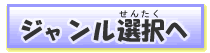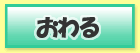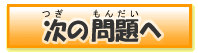|
|

|
|
正解 1 築造(に協力(した人(や僧侶(の名前(
「土塔(」は、奈良時代(に僧(行基(らによって土(と瓦(で築(かれた十三重(の塔(です。復元整備(を目的(とした発掘調査(の結果(、一辺(53.1メートル(180尺()で四角錐(の頂部(をカットしたような形(であることがわかりました。土台(となる基壇(の上(に四角(の段(が12層(、円形(の段(が1層(あり、その上部(には小規模(な建物(があったと思(われます。さらに各層(には瓦(を葺(いています。出土(した瓦(には、へら状(の工具(を用(いて文字(を記(した瓦(が1,000点(以上(あり、その大半(は人名(が記(されたものです。僧名(、出家(していない信者(、豪族(、一般民衆(といった様々(な階層(の名前(があります。 |
|
|
|
|